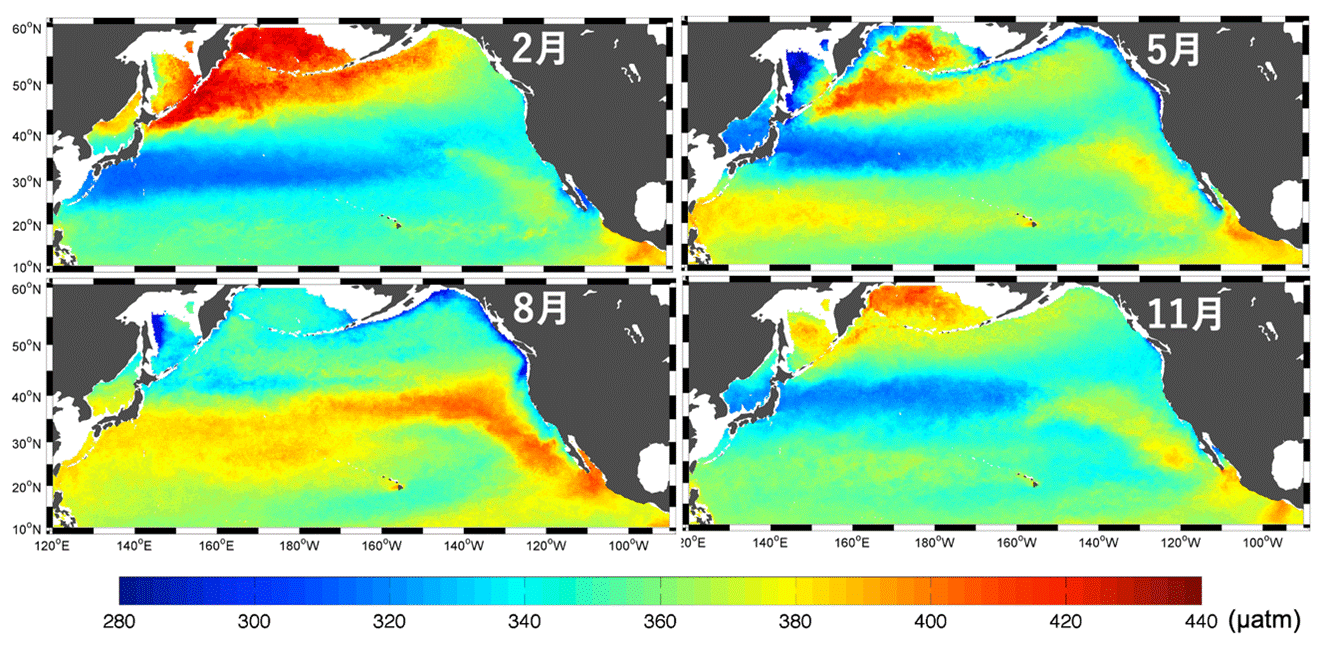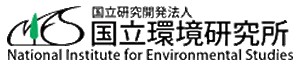日本-北米航路
概要と成果
日本-北米航路では1995年から洋上大気と海洋表層水の温室効果ガス観測を行っています。1995年から1999年まで協力を得たカナダのSeaboard International Shipping Co.所属の材木運搬船「SKAUGRAN」は、バンクーバー(カナダ)・シアトル(米国)・ロサンゼルス(米国)と日本の各港(苫小牧・仙台・東京・北九州等)を寄港地として日本-北米西岸間を6〜7週間で行き来し、計37往復で観測を行いました。
1999年から2001年まで協力を得た(株)商船三井所属のコンテナ船「ALLIGATOR HOPE」は、東京とバンクーバー(カナダ)の間を5週間周期で航行し、特に北太平洋高緯度海域の高頻度観測を計16往復行いました。
2001年からはトヨフジ海運(株)が本事業に参画し、現在まで20年以上も観測が継続されています(船舶の変更に伴う中断期間を除く)。2001年から2013年まで観測を担った自動車運搬船「PYXIS」と2014年から現在まで観測を担っている「NEW CENTURY 2」(写真)は愛知県田原港を母港として、北米西海岸を往復する航路とパナマ運河を経由して北米東海岸を往復する航路の2つの航路で運航されており、2023年末までに約170往復の観測を実現しました。

これまでの観測から、海洋表層二酸化炭素(CO2)濃度(分圧)の季節変化(図)や年々変化を明らかにすることができました。大気中CO2濃度の季節変化は最大でも20 ppm程度であるのに対して、海洋表層CO2分圧は最大で150 ppm(µatm)に達し、海洋の循環や生物活動によって時空間的に大きな変化を示していることが分かります。北太平洋は、海洋生物による生産活動が活発な海域であり、それによって海洋表層CO2分圧が顕著に低下しています。海洋の温暖化や酸性化に伴って海洋循環や生物活動が変化すると、それらの影響で海洋表層CO2分布も変化することが考えられるため、観測による監視が今後も必要です。