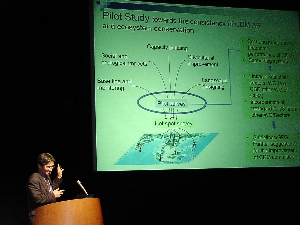「生物多様性・生態系保全と京都メカニズム」に関する国際シンポジウム・ワークショップ
報告:国立環境研究所 生物圏環境研究領域 奥田敏統
国立環境研究所は森林総合研究所、早稲田大学環境総合研究センター、地球環境戦略機関(IGES)、国立民族学博物館共同で、 平成16年1月29~30日に早稲田大学において京都メカニズムの一つであるCDM(Clean Development Mechanism)と多様性保全に関する 国際シンポジウム・ワークショップを開催した(後援: 環境省、林野庁、東京大学大学院農学生命科学研究科、広島大学大学院 国際協力研究科、WWFジャパン)。2日間で延べ700人の参加があり、地球温暖化や生物多様性に対する関心の高さがうかがえた。 以下本会議に関する趣旨・背景および会議で取り上げられたポイントなどについて概略する。まず、そもそも京都議定書のCDMと 生物多様性保全がどう関連するのか述べたい。
京都議定書では他の国で削減目標を達成する仕組み-いわゆる京都メカニズムが導入されている。すなわち先進国間(付属書B国のみ)で 排出枠(削減目標の割り当量)の一部を取り引きする仕組み(排出量取引)、同じく先進国間(付属書I国)で温室効果ガスの削減または 吸収源活動を共同で実施し、そこから生じた排出量を投資国が獲得する仕組み(共同実施)および、先進国(付属書I国)と 途上国(非付属書I国)との間で、削減・吸収源活動を行い、その結果発生した排出削減量を資金・技術援助を行った先進国が獲得する 仕組み(クリーン開発メカニズム、CDM)である。ロシアなどのように基準年に対して排出量がマイナスになっている国との間で 排出量取引を行った場合は地球全体で見れば実質的には、温室効果ガスは削減されないことになるが、CDMでは吸収源の拡大に加えて、 途上国での削減技術や森林の修復技術の向上などのボトムアップや地域社会の活性化などが期待されている。
ここで注意せねばならないのは吸収源CDM活動が行われるのは発展途上国という点である。しかもその多くは南の国、すなわち熱帯から 亜熱帯地域に分布する。当然ことながらこの地域での木を植えたり(森を切り開いたり)の活動は、熱帯林やそれを取り巻くランドスケープ の保全に深く関わってくる話である。熱帯林は地球上で最も多様性の高い生物相を育む生態系であり、大木が生い茂る森の平均的な地上部 現存量は地球上のどの森林生態系よりも高い。一方で1980年代頃からの世界の急激な森林面積の減少の殆どが熱帯地域で起こったもの であり、その直接的な原因は大規模な農地への土地利用転換や森林伐採であるが、その背景には当該地域の貧困や土地利用政策、 人口移住政策の失敗、貧富の格差問題などが深く根ざしているといわれている。
こうした熱帯地域の生態系や地域社会の複雑性が故に、吸収源CDM活動に関しては、吸収量把握の不確実性、植林活動による CDM対象域外での森林伐採や農地への土地利用転換活動の助長(リーケッジ)や地域社会、経済に与える影響などについても十分な配慮が 必要である。またCDM吸収源活動では、短期間での炭素蓄積量の獲得が最大関心事になる可能性が強く、その場合、ユーカリやアカシアなどの 早生樹種を用いた造林が主体になることは容易に想像できる。こうした単調な森林が大規模に出現することで地域の生態系の生物相の組成や 地力などの低下につながるとの危惧や、外来種の持ち込みに対しての強い懸念がある。さらにヨーロッパや島嶼国の中にはこうしたCDM活動が 先進国で温室効果ガス削減の抜け道になると強く反対する国もあるほどである。(これらのメカニズムを温室効果ガス削減の抜け穴と主張する 国や団体もある)。
とはいえ、一方で破壊し尽くされ劣化した当該地域の生態系を修復させるためには、インセンティブ導入が必要不可欠であり、 温暖化ビジネスとしてのCDM活動は熱帯地域の緑の面積拡大やさらなる生態系の崩壊(土壌浸食など)を食い止めるという点において、 大きな期待が寄せられているのも事実だ。むしろ、CDM吸収源活動は森林管理や途上国の資源管理を支援するための足がかりとして捉える ことも出来るのである。森林伐採後の荒廃した生態系復元、多様性保全を国家や州政府のスローガンとして掲げながらも、現実に行うと なれば様々な障害があり、事業展開の切っ掛けすらもるつかみ倦ねている国や地域が多いのではなかろうか。国民や地域社会の「明日の生活」 に直接的な関わりが薄い自然保護関係の問題への対応は、何らかの国際的な縛りやmotivationがない限り、先送りされがちで、 また行政当局にっとっても、具体的な対応がとりにくいのも確かである。
今回の国際シンポジウム・ワークショップでの主目的は、熱帯地域の生態系保全(これは地域社会の保全も含める)に配慮しつつ、 CDM吸収源活動を円滑に行うにはどうすればよいかという点について、行政、企業(CDM事業者)、NGO、研究機関の関係者が一堂に会し 問題点を認識し、あらたな対応方法を考えるということにあった。昨年末にミラノで開催されたCOP9(気候変動枠組条約第9回締約国会合) では温暖化対策と生物多様性保全や砂漠化防止などとのリンケージを推進すべきでるとする意見が多数の国や団体から提出されていたが、 いざ、こうした複数領域に関わる問題に立ち入ろうとすれば(この場合は温暖化対策と多様性保全や熱帯林の破壊)、 それぞれの領域関係者の間で土地利用や資源管理に対する認識のズレが大きいことに気づく。例えば「森林管理」についても京都議定書で 謳われているものと、生態系や多様性保全を意識した森林認証制度などでは「管理」そのものに対する認識・視点も異なる。 こうした背景から、今回のシンポ・ワークショップでは、温暖化対策と生物多様性、熱帯地域での社会経済や森林管理に関わる専門家を 招聘し、まずそれぞれの立場でのCDM活動や熱帯地域保全について語って頂いた。
1日目のシンポジウムでは、世界銀行のロバートワトソン氏の基調講演に始まり、昨年末のCOP9で合意された吸収源CDM実施に関する細則の 紹介(林野庁佐藤氏)、熱帯地域での土地利用変化や森林減少の現状と背景(国連食糧農業機関、樫尾氏)、熱帯地域社会の現状(東京大学、 井上氏)、インドでの事例をもとにしたCDMなどの植林活動がもたらす社会的効果・影響(インドエネルギー資源研究所、シン氏)などの 発表講演があった。続い同日の午後からはCDM活動と生態系保全の両立をどうするかというテーマについて、アマゾンでのこれまでの 森林減少と生物多様性に関する研究報告(ブラジル国立アマゾン研究所、メスキタ氏)、カナダ政府が推進するモデルフォレストと 森林管理保全のCDM活動への適用の可能性について(カナダ林野局)、我が国の研究機関が進めるCDMに関連した調査研究活動 (森林総研清野氏)、CDM活動へのエコシステムマネージメント概念の適用性について(環境研、奥田)の講演が行われた。 総合討論では国際林業研究センター(CIFOR)が提唱する生態系保全のためのクライテリア・インディケーターについて、 (CIFOR,藤間氏)、CDMを行う際の費用対効果について(地球環境戦略研究機関:IGES、小林氏)からの話題提供があった。
1日目のシンポジウムがこれまでのCDMや熱帯林にかかわる諸問題の紹介に重点を置いたのに対し、2日目のワークショップでは、 今後多くのCDM事業の展開が見込まれる東南アジアの熱帯地域での諸事情に焦点を絞って会議を行った。まず、世銀のノーブル氏が 東南アジア地域でのCDM事業の新たな展開の可能性について基調講演を行い、そのあと、前日の復習を兼ねてIGESの小林氏が CDMを実践する上での諸問題ついて講演を行った。その次のセッションでは吸収源CDM活動の今後の展開が予測される場所や パイロット的に事業展開が行われている箇所の紹介があった(インドネシア林業省のマスリパティン氏、フィリピン大学のラスコ氏、 ベトナム農開発省便hし、環境省佐川氏)。午後のセッションではCDM活動を行うにあたり、生態系保全のためには何に注意を払う 必要があるのか、またどのような研究的な支援がありうるのかという点に焦点をあて、CIFORのマルディアッソ氏が生物多様性保全の ためのクライテリアとインディケーターについて、環境研究所の椿氏が野生生物の空間分布を予測手法について、広島大学中越氏が ランドスケープ保全の立場から植生配置と多様性との関係について、フィリピン大学のプルフィン氏が地域住民との合意形成のあり方 について発表を行った。最後の総合討論では、吸収源CDM活動を実践する企業の立場から、海外産業植林センターの田野岡氏、 住友林業の小林氏、日商岩井総合研究所の中島氏からそれぞれの事業・研究サイトおよび、CDMのメカニズムそのものについての 問題提起があった。
会議中様々な質問やコメントがあったが、特にCDMの実践と多様性とのリンケージという点に関してはいえば、論点は多様性や 地域の生態系保全に配慮するための様々な施策を実行する上での費用を誰が負担し、いかに地域社会との共存共栄をはかりながら CDMを進められるか、さらには事業関係者や行政・研究機関などがどのような協力関係によってどのような支援ができるかなどの点に 集約される。また、先のCOP9で合意された吸収源CDMに関する細則では、CDM実施にあったては環境影響に加えて地域の社会・経済的影響 の分析を行うことが明記されているが、こうした調査や分析にかかる費用はCDM事業実施者の直接的な負担になる。
吸収源CDM活動によるCER(認証された排出削減量)が高値で取引されるようなインセンティブやプレミアム的な価値が出てくる ようなメカニズムが働けば話は別であるが、吸収源活動CDMの不確実性や非永続性を考えれば、投資する側にとっては期待されるほど 魅力的なものにはならない可能性もある。さらに環境影響評価にかかるコストやCDMによって生じたリーケッジへの対処およびその フォローなどにかかる費用を考えれば、CERの値段によってはまったく見合わないケースが出てくることも予想される。林業家や 木材企業などからみれば、面倒な手続やそれにかかる費用まで捻出してCDMを行うよりは普通に植林事業を行う方が、 費用対効果は高くなる-そう考えるのは当然かもしれない。ましてや、小規模CDM造林プロジェクトでは、認証に関わる経費が 相対的に高くなるため、環境影響評価の調査項目も、より簡素化してほしいとの要望が上がるの無理もない話である (COP9では認証や検証にかかる経費削減のルールが適用されることになっている)。
ところで森林を再生するとは何も炭素蓄積機能を増やすことだけではない。森林は土砂流出防止機能、大気成分調節機能、 多様性保全機能、リクレーションや環境教育の場としての機能などさまざまなエコロジカルサービスを提供する。たとえば、 同じ木を植える場合でも、野生動物にとって利用しやすい樹木を植えたり、動物の生息環境や行動パターンを考慮した植生の 空間配置にすれば、よりエコロジカルサービスの価値は高まる。CDM活動によって副次的に得られるこうしたエコロジカルサービスは CERの付加価値として加えられるべきものであろうが、値段が高いだけで不確実性の要素が強く将来性が見えなければ誰も投資しない。 すなわち、前述のように環境に配慮した森を作る場合の余分なコストや認証にかかる費用は誰が負担するのかという点にどうしても たどり着いてしまう。あらたな植林活動にともなって生じたエコロジカルサービスを享受するのはその地域に住む人々であるので、 地域やホスト国が負担すべきであるとの考えもあろうが、熱帯地域や開発途上国の劣化した生態系を復元し、豊かな森をつくることは 長期的には地球環境の蘇生につながることでもあるので、CDMにかかる最低限の費用は別として、その土台作りに先進国がなんらかの 財政的な支援を行っても良いのではなかろうか。それが呼び水になって吸収源CDM活動が、うまく回り始めるのであればそれは 願ってもないことである。また、技術的な支援についてはホスト国およびドナーとなる研究機関、行政機関、民間やNGOから人的 パワーを拠出し、単なる審査や検査を行うことを目的とするのではなく、植林技術の改良やランドスケープ全体の保全を考えた生態系の 修復技術の導入を推進するようなアドバイザリーボードをそれぞれの地域や国に設置することが必要になってくるであろう。 またそのための準備を早急に開始すべきではないかと考える。